
色丹島での墓参の様子(2013年)
軍国主義日本に対する戦勝記念日であり、第二次世界大戦終結の日――。ロシアは今年7月、一方的に9月3日を「対日戦勝記念日」と制定した。ウクライナ戦争をきっかけに、関係が悪化している日本を牽制する動きとみられる。第二次世界大戦の終戦直前に日ソ中立条約を無視して突如、参戦してきた旧ソ連軍は1945年9月5日までに、日本固有の領土である北方領土の占領を終えた。
その北方領土では、ウクライナ戦争前まで夏から初秋にかけて日露の民間交流が盛んであった。しかし現在、領土返還交渉やビザなし交流は中断。元島民による墓参もストップしている。筆者は過去に3度、北方領土を取材した。本稿では、当時の現地の状況とともに墓参の様子を紹介したい。(JBプレス2023/9/3)
日本人集落の面影は消え去ったが…
私が初めて北方領土の択捉島を訪れたのは2012(平成24)年のことであった。ビザなし交流団員として参加した。2013(平成25)年には色丹島、2015(平成27)年には択捉島と国後島を訪問している。ちなみに根室半島からも近い距離にある歯舞群島は、ビザなし交流の中には組み込まれていない。
2012年に択捉島を訪れた時、ソ連の侵攻を打電した郵便局が現存していた。だが3年後の2015年に再訪した時には取り壊され、北方領土における日本の建物は姿を消した。日本のムラの跡をいくつか訪問したが、そこにはかつての日本人集落の面影はまったくない。

ソ連軍が攻めてきた時に打電した択捉島の郵便局(2012年撮影)。現在は取り壊されてしまっている
ロシア人が暮らす集落は、ペンキでカラフルに塗られた建物が並び、異国情緒が漂う。ロシア人の心の拠り所になっているロシア正教会の鐘の音が集落に時折、響き渡っていた。
択捉島の資料館に残っていた寺の梵鐘…
現地での日本の痕跡といえば、ロシアに接収された家財道具などが展示されている資料館が択捉島にあるくらい。そこで寺の梵鐘を見つけた時には、心が痛んだ。戦前の北方領土には寺を中心とするムラ社会が存在した、数少ない証である。

択捉島のに残されていた寺の梵鐘

択捉島の集落と日本人墓地。ロシア人墓地も入り込んでいる(2015年)

倒れて地面にのめり込んだ墓もある(択捉島、2015年)
では、北方領土のうち、色丹島と仏教寺院の関係性を紹介しよう。色丹島は根室・納沙布岬から北東におよそ70kmの距離に位置する。約24km×10kmの長方形の島である。

色丹島に残る戦車(2013年)
島全体が丘陵地帯になっていて、湿原が点在する。そこは高山植物や日本でも絶滅した動植物が存在し、実にダイナミックで美しい情景が広がる。仮に領土が返還されたら、特にこの色丹島はエコツアー好きには、たまらない聖地になることだろう。
実は色丹島は明治初期、島全体が浄土宗の増上寺(東京都港区)の寺領だったという知られざる過去をもつ。それを解き明かすには、少し島の歴史を振り返る必要がある。
北方領土への移民コミュニティだった寺院
北方領土は過去一度も外国の領土になったことのない日本固有の領土である。江戸時代、幕府は北方四島・千島列島・樺太の蝦夷地を日本の直轄領として開拓に着手。1855(安政元)年の日露通好条約においては、択捉島の北側に引かれた国境を、両国が確認している。
色丹島は、北方領土海域で漁をする船の避難港として整備された。そして北方領土海域は世界でも有数の漁場として発展していく。
明治に入ると、北海道は新政府によって本格的に開拓が進められることになる。しかし、北海道はあまりにも広く、また新政府の予算も潤沢ではなかったため、地方の藩や有力寺院などに土地を分け与えて支配させたのである。これを分領支配という。
1869(明治2)年、東本願寺(真宗大谷派)や増上寺(浄土宗)が開拓事業に参画すべく、新政府に申し出ると、同年9月に増上寺に充てがわれた地域のひとつが色丹島であった。この時、正式に増上寺の寺領として組み込まれている。
だが、増上寺の寺領であったのはわずか1年ほど。1870(明治3)年に新政府に上知(土地の没収)されている。当時、日本は神仏分離政策を断行中であり、仏教への風当たりが強かった。寺院の境内は、宗教儀式で使うための土地以外はことごとく没収されている。
先に述べたように明治期以降、北方領土を含む北海道全土に、寺院(神社も)が次々と進出。本州からムラ単位で入植する際に、寺院・神社が一緒にくっついていった。
つまり寺院は、移民のコミュニティを強化する役割であり、故郷の象徴でもあり、開拓中に死んでいったムラ人の弔いの場だったのだ。これは明治時代以降に行われたブラジルやハワイへの移住と同じ構図である。
仏教各宗派が寺院を建立
実際、北方領土には多くの寺が建設された。浄土真宗本願寺派、真宗大谷派、浄土宗、曹洞宗、日蓮宗など計24の寺院(無人の地蔵堂などを含む)が建立されたとの記録が残っている。
1945(昭和20)年のソ連の侵攻時、北方四島の日本人はおよそ1万7000人。人口に対する寺院数(寺院密度)はかなり多かったとみてよい。
現在は領土の帰属をめぐって日露間で紛争中であるため、寺院の調査は事実上、ほとんど手付かずである。北海道神社庁とロシア・サハリン州が2005(平成17)年にまとめた共同学術調査報告書が唯一、存在する。
日本の寺院はソ連の侵攻とともに全て破壊され、現在はかろうじて石垣が残っている程度だ。しかし、集落の外れには日本人島民の墓地が、比較的、良好な状態で残されていた。
1964(昭和39)年から続けられ、ウクライナ戦争による日露関係の悪化で中断している墓参(北方墓参、ビザなし交流)は、元島民にとって極めて大切な行事である。これは、北方領土に残された先祖代々の墓に手を合わせたいという元島民の願いを、人道的立場に沿って旧ソ連が受け入れたものだ。墓参にはロシア人島民も参加する。墓参りを通じた、日露の民間交流の場となっていた。
話を色丹島に戻す。私は島の墓地のひとつ稲茂尻墓地を訪れた。周辺は湿地帯が広がり、何基かの墓石が点在する。そこは、えも言われぬ絶景墓地であった。戦後70年以上が経過しているにもかかわらず、下草などが刈られ、きちんと管理されていたことには驚いた。
聞けば、日本人がお参りしやすいように日頃、ロシア島民が管理をしているという。択捉島や国後島の墓地においても、一部倒れている墓や林に埋もれつつある墓もあるが、比較的きちんと維持されてきている印象があった。
墓石に漢字で刻まれた没年や戒名
むしろ、ロシア人墓地のほうが、草が茫々で荒れ果てていた。これは、ロシア人にとって北方領土が過酷な場所であることを表している。現地の不便な生活に耐えきれず、内地のモスクワなどに引っ越してしまい、そのまま墓が放置されてしまったからだ。

国後島島の日本人墓地(2015年)
国後島のロシア人墓地。草ぼうぼうで荒れ果てていた(2015年)
ロシアに実効支配されている地とはいえ、「和の存在感」を示しているのが日本人の墓である。墓石には没年や戒名などが漢字で刻まれている。墓石は、いくらロシアが、自国領であることを主張しようとも、そこがかつては日本固有の領土であったことを証明しているのである。
私たちは、そこで手を合わせ、故郷に残り続ける故人に語りかける。それはいつ訪れても、胸が熱くなる光景である。元島民らは「いつでも墓参りできるようにしてほしい」と訴える。墓は「故郷そのもの」なのだ。
しかし、昨年から続くウクライナ戦争によって、北方領土交渉は断絶。ビザなし交流再開の目処は立たない。元島民の平均年齢は現在87歳。北方領土で墓参りするには、限界の年齢が近づいている。(鵜飼 秀徳:作家、正覚寺住職、大正大学招聘教授)



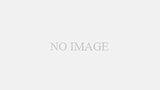
コメント