北方領土ビザなし交流の開始30年を来年に控え、根室市は7月17日、四島との交流や往来のあり方などを検討する「専門家会議」を設置する。ビザなし交流や文化財保護などの専門家5人を委員に任命、講演会やシンポジウムなどを定期開催し、市民参加型の取り組みにする考えだ。
石垣雅敏市長が29日の定例記者会見で発表し「領土問題を科学的に検討し、四島との往来を目指した知識の積み上げをする。領土問題を考える新たなスタートにしたい」と狙いを語った。当面の検討課題として①四島の地域間交流②自由往来・自由交易③歴史・文化遺産の保存と活用—の3点を挙げた。(武藤里美)
担当の谷内紀夫・市北方領土対策監は「報告書にまとめて終わりではなく、いかに現実の取り組みにつなげるか」を議論するという。さらに「根室と四島がいつでも話せるような基盤を持つこと」を最終目標に掲げ「領土交渉は国がやることだが、顔が見える近所づきあいの中でできることもあるはず」と強調する。
委員には岩手県立大学の黒岩幸子教授、北海道国際交流・協力センターの高田喜博客員研究員、根室市史編さん委員の桐澤国男さん、札幌大学の川上淳教授、北海道博物館の右代啓視学芸員の5人を委嘱する。
また、終戦まで根室と国後島を結んだ電話用の海底ケーブルの中継施設「陸揚庫」については分科会を設置する。陸揚庫は国の有形文化財登録に向けた手続きが進んでおり、分科会は2023年3月までに保存と活用の指針を示す。
石垣市長は専門家会議の新設を公約に掲げ、昨年3月の設置を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で遅れていた。
7月17日にシンポジウム
専門家会議の初回の講演会とシンポジウムは「根室から考える『ビザなし』のこれまでとこれから」と題して、7月17日午後1時半から道立北方四島交流センター(市内穂香)で開かれる。
第1部は専門家会議委員で、岩手県立大学の黒岩幸子教授が地域間交流の可能性について基調講演する。
第2部では黒岩教授、千島歯舞諸島居住者連盟の河田弘登志副理事長、色丹島元島民の得能宏さん、根室商工会議所の山本連治郎会頭、ビザなしサポーターズたんぽぽの本田幹子さんが登壇し、ビザなし交流の歴史と今後を語り合う。これに合わせて7月13日~25日、根室市は同センターでビザなし交流開始時の新聞記事などを展示する。



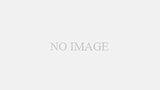
コメント