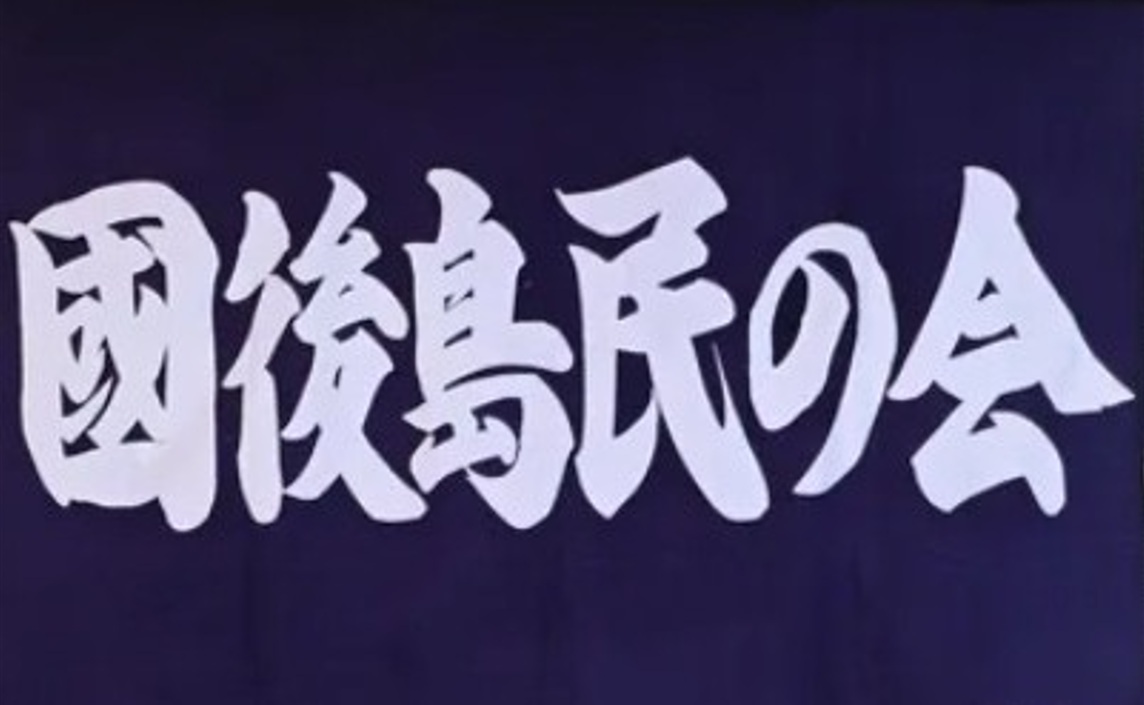今年2月、根室市内で開かれた北方領土問題研修会(千島歯舞諸島居住者連盟など主催)で、北海道博物館の右代啓視学芸員が「北方四島の歴史・文化と継承」と題して講演した。右代さんは、北方四島ビザなし交流の枠組みの中で、2006年から「歴史文化専門家」として毎年、北方四島を訪問し、通常のビザなし交流や自由訪問、北方墓参では立ち入ることが出来ない島の奥深いところまで踏み入って、アイヌ文化期の遺跡や戦前の日本の建築物、遺構などの現地調査を行ってきた人である。
講演の中で、右代さんは「北方四島ナショナルセンター」の必要性を強調した。四島で生まれ育ち、実体験を語ることが出来る元島民がいずれいなくなる時に備えて、元島民の思いや北方四島の歴史や文化を継承するための持続可能なシステム・組織づくりを訴えたのだった。
私が根室市で仕事をしていた2021年、市では「北方領土対策に関する専門家会議」を立ち上げた。当面の検討課題として「四島との地域間交流」「四島との自由往来・自由交易」「四島に関連する歴史・文化遺産の保存、継承、活用」を掲げた。
「歴史・文化遺産の保存、継承、活用」の中では、北方四島に残る日本人墓地や墓石、日本の建造物や遺構などの修復と保全に向けた手法の検討をはじめ、根室側に残る四島関連遺産をつないで活用を図る「北方領土遺産コリドール(回廊)」構想の取りまとめを想定していた。
当時、庁内説明用に作成した資料やポンチ絵には、もう1つ、国立のメモリアル施設として「(仮称)北方平和祈念資料館」構想づくりというのがあった。広島や長崎の原爆資料館、沖縄の平和祈念資料館のようなシンボル的な施設を思い描いていた。右代さんにも専門家会議の委員になってもらったが、新型コロナの感染拡大と重なったことで、具体的な議論に入ることが出来ず、構想は幻に終わってしまった。
北海道根室振興局時代を含めて十数年、北方領土関係の仕事をする中で、存外「北方領土の専門家」がいないことに気づかされた。日露関係、領土交渉、漁業、軍事などの分野で専門家は多数存在するが、たとえば「北方四島にソ連軍はどのように侵攻したのか」「ソ連占領下の四島でどのように社会主義が導入されたのか」「ロシア人との混住時代に島民はどうのように暮らしたのか」「脱出や強制退去の途中で何人の島民が遭難や病気で亡くなったのか」といった北方領土に特化したテーマでは十分な調査や研究が行われず、もっぱら元島民の記憶に頼ったり、ソ連側の資料を探すほかない状況だった。
右代さんの講演を聴いて、すっかり忘れていた「北方平和祈念資料館構想」が再び頭をもたげてきた。
4月は元島民や後継者でつくる千島歯舞諸島居住者連盟の各支部の総会が行われる。その先陣を切って3月、私が所属している「国後島民の会」の令和7年度総会が根室市内で開かれた。総会では、島民の会としての決議を採択して、関係機関に送付するのだが、戦後80年の今年の決議の中に、中断している北方墓参の再開などと併せて、右代さんの「北方四島ナショナルセンター」に触発されて「北方領土・知の拠点構想」を盛り込んだ。以下、総会決議を紹介し、今回の隣接地域からの報告とさせていただく。
≪総会決議≫
我々の故郷である北方領土が旧ソ連、そしてロシアに不法占拠されてから、80年の歳月が流れた。終戦時、1万7千人以上いた元島民は、終戦後に北方四島で生まれた「新元島民」を含めて5,275人と3分の1以下に減少し、平均年齢は88.5歳となっている。
この間の領土交渉を振り返れば、その時々の国内外の情勢変化に大きく影響され、半歩前進したかと思えば、一歩後退する、そんなもどかしい状況の繰り返しであった。
とりわけ、コロナ禍でビザなし渡航がすべて止まった2020年から、ウクライナ戦争を経て、日ロ政府間の対話が杜絶し、人的・文化的交流、さらには北方四島周辺水域における安全操業などの経済活動も停止している現状を見れば、二歩も三歩も後退した感は否めない。
我々は、日本政府に対して、ウクライナ戦争の終結に向けた動きを注視しながら、領土交渉の再開に向けて時期を逃さず取り組むよう要請するとともに、何よりもまず、5年間実施できていない北方墓参の即時再開を強く求めるものである。
北方墓参は、旧ソ連が領土問題は存在しないとしていた冬の時代でさえ、人道的観点から実施されてきたものである。最後にもう一度、故郷の島の土を踏みたいと切に願いながら、この5年の間にいったい何人の元島民が亡くなっていったことか ―。
我々は、日本政府に対して、堂々と、力強く、そして繰り返しロシア側に墓参再開の申し入れを行うよう要請するとともに、北方領土を不法に占拠しているロシア政府に対しても、最低限の人道上の義務として北方墓参再開の申し入れを無条件で受け入れるよう強く求めるものである。
同時に、領土問題解決に向けた道筋が全く描けない現状に鑑み、国内措置で今すぐにでも解決できる元島民への援護対策、即ち「残地財産の保全と残地財産権の不行使に対する補償問題等の解決」、さらには、今後の返還要求運動の担い手となるすべての後継者に対して元島民と同様の権利を認めて借入資格者とする「融資制度の改正」について早急に取り組み、解決を図るよう関係機関に重ねて要求する。
ロシアに目を向けると、「対日戦勝と第二次世界大戦の終結80周年」を大々的に喧伝し、旧ソ連軍の千島列島上陸作戦を称える軍事愛国博物館を占守島に建設するなど、若い世代への軍事愛国教育、都合の良い歴史教育を強力に推し進めている。
我々は、返還要求運動のさらなる長期化も視野に入れ、元島民の体験や記憶、四島ヘの思いを後世に引き継ぎ、正しい歴史認識の普及や後継者を育成するために、返還要求運動を将来にわたって持続可能なものとする基盤や仕組みの整備が、今こそ求められていると考える。
そこで、北方領土に関する歴史、文化、産業、生活を網羅した「展示・資料収集機能」、北方領土のあらゆる分野をテーマとする学術的な「調査・研究・提言機能」、さらには、全国の若い世代を対象とする北方領土学習や返還要求運動を担う後継者の育成を図る「学習・人材育成機能」を備えたナショナルセンターとして「(仮称)北方領土・知の拠点構想」を提唱する。
国後島民の会は、迎えた戦後80年の節目に、望郷と無念のうちに他界した1万2千人になんなんとする先達の遺志を受け継ぎ、北方領土の即時一括返還と元島民と後継者に対する援護対策の充実を旗印に掲げ、ぶれることなく邁進する決意を、改めてここに表明する。
上記決議する 令和7年3月16日
【ボストーク61号(NPO法人ロシア極東研機関誌)2025年4月15日発行】